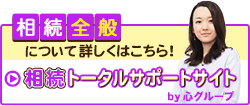婚姻することになった場合、婚姻届けを作成し、役所に提出することになります。
役所では、提出された書面に不備がないかを形式的に審査するだけなので、婚姻が無効かどうかについては判断しません。
つまり、提出された書面に不備がなければ、「とりあえず有効な婚姻関係が成立した」という扱いになります。
しかし、法律では、婚姻が無効になる場合について、規定が定められています。
その1つとして、「婚姻の意思がない」というものがあります。
つまり、婚姻届けを出したものの、実際は「婚姻の意思がない」場合、婚姻は無効になるということです。
では、どういった場合に、「婚姻の意思がない」ということになるのでしょうか。
この点について、最高裁は「当事者間に真に社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指す」と判示しています。
さらに、「法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあったと認めうる場合であっても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎない」場合、婚姻は無効になるとも判示しています。
この判決内容からすると、たとえば日本でのビザを取得することだけを目的に、婚姻届けを提出したような場合は、婚姻が無効になることもあり得るでしょう。
では、長期間同棲していたカップルが、余命わずかの時に婚姻届けを提出した場合はどうでしょうか。
たとえばAさんが余命わずかの状態で、交際相手のBさんと婚姻すれば、BさんはAさんの遺産を相続することができるようになります。
そうなれば、Aさんの親族は、「遺産目当ての婚姻だ」などと主張し、弁護士に裁判の依頼をすることが予想されます。
もし、最高裁が述べる「真に社会通念上夫婦であると認められる関係」というものが、『婚姻届けを出した後も、夫婦として共同生活を送ること』を指していると考えると、まもなく死別してしまう2人には、婚姻の意思がないと評価する余地が出てきます。
しかし、この点がまさに争点になった裁判では、婚姻が有効なものであると判断しました。
つまり、最高裁は、婚姻届けを出した後も、ずっと一緒に暮らしていくことまでは必要ないと考えていると言えるでしょう。