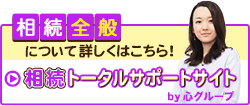自己破産の手続きを進める場合、一定の財産がある場合は、基本的に管財事件となります。
管財事件になれば、管財人が財産の調査を行ったり、免責不許可事由の調査を行うなど、手続きが重たくなってしまい、管財人の費用も用意しなければならないなど、破産申し立てをする方にとっては、負担が大きくなります。
自己破産の申し立てを行う方が、不動産を所有している場合、その不動産を売却し、債権者へお金を分配しなければならないため、原則として管財事件になります。
しかし、大阪地裁では、不動産がある場合であっても、同時廃止(管財人が就かない手続き)になる場合があります。
まず、条件の一つが、不動産に抵当権が入っている場合です。
たとえば、住宅ローンを組んで、家を購入したようなケースでは、土地や家に抵当権が入っていることがほとんどだと思います。
次に、残ローンが、固定資産税評価額の2倍を超えていることが条件になります。
たとえば、固定資産税評価額が500万円で、残ローンが1000万円を超えている場合は、条件を満たすということになります。
他方、残ローンが、固定資産税評価額の2倍には届かない場合であっても、1.5倍から2倍までには達する場合で、かつ、残ローンが査定書の評価額の1.5倍を超える場合も、条件を満たします。
では、なぜこれらのケースでは、同時廃止で手続きを進められるかですが、その理由はシンプルで、『仮に不動産を売却しても、債権者への分配ができない」からです。
つまり、不動産を売却した場合、抵当権者が優先権を持っているため、管財人が不動産を売却しても、結局、他の債権者への分配はできないということになるのです。
たとえば、不動産が400万円で売れて、残ローンが600万円の場合、売却代金の400万円は、全残ローンの返済にあてられてしまい、他の債権者に分配することができません。
このようなケースで、あえて手間と時間がかけてまで、管財事件にする実益が乏しいため、同時廃止にできるという運用がなされています。
そのため、本来なら同時廃止にできるはずが、不動産があるからという理由だけで、最初から管財事件として申し立てをすることは好ましくありません。
不動産をお持ちの方が自己破産をする際は、弁護士に対し、そのあたりの見通しも聞いてみるとよろしいかと思います。