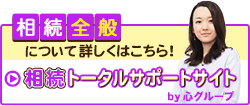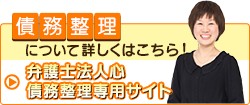破産手続きを検討している方は、借金の返済ができなくなって、訴訟を起こされているケースが少なくありません。
借金をしたことが事実であれば、訴訟で戦っても勝つことは難しいため、債権者が求めるとおりの判決が出てしまいます。
そうなってしまうと、強制執行が可能になるため、預貯金口座の差し押さえや、給料の差し押さえと言った事態が生じてしまいます。
それらの事態を防ぐためには、早めに破産手続きを進めてしまうことが有効です。
つまり、裁判所に破産の申し立てを行い、破産手続開始決定が出れば、訴訟手続きが中断するという効果がありますので、一刻も早く破産手続きを進める必要があるのです。
もっとも、破産手続開始決定が出ても、中断されない訴訟というものもあります。
破産手続きは、あくまで財産的な権利関係を一律で処理するというものですので、財産的な権利関係と無関係の訴訟は中断されません。
たとえば、離婚訴訟などが代表例です。
破産する方が離婚するかどうかは、財産権とは関係ありませんので、破産手続きが始まっても、そのまま離婚の審理が続きます。
また、会社が破産する場合に、会社の組織に関する裁判も、中断はしません。
たとえば、会社分割や役員の解任について、無効の裁判を行うケースなどが代表例です。
このように、破産手続きと訴訟は、複雑な関係性にありますので、詳細は弁護士にご相談ください。