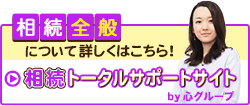遺留分という制度をご存知でしょうか。
遺留分は、相続人に認められた、最低限度の権利です。
仮に、亡くなった方が遺言書で「全財産を長女に相続させる」といった記載をしたとしても、二女や三女は、法律の割合の半分までは自己の権利を主張できます。
ただし、遺留分の権利は、子や孫などの直系の子孫、親や祖父母などの直系の祖先にのみ認められています。
亡くなった方の兄弟姉妹や、甥姪には遺留分が認められていないため、注意が必要です。
かつての制度では、遺留分の権利を行使すると、原則として遺産の全てに対して、少しずつ権利を主張できることになっていました。
たとえば、相続人が長女と二女の2人で「全財産を長女に相続させる」という遺言書があった場合、二女は遺産の4分の1については、権利を主張できます。
その結果、長女が取得した不動産について4分の1の権利を取得し、長女が取得した預貯金についても4分の1を取得するといったように、全ての遺産について4分の1ずつの権利を主張できるようになります。
しかし、この制度はとても使い勝手が悪い制度であると批判をされていました。
たとえば、たくさんの不動産を残して亡くなり、預金があまりないケースで、遺留分の権利を主張するとどうなるでしょうか。
各不動産について、長女が4分の3の権利を取得し、二女が4分の1の権利を取得することになるため、協力して不動産を管理する必要があります。
しかし、不平等な遺言書を残された長女と二女は、仲が悪いことが多く、不動産の管理をうまくできない可能性が高いです。
他にも不都合なケースがあります。
亡くなった経営者は、長男に会社を受け継がせたいと考え、株を長男に相続させたのに、二男が遺留分の権利を行使すると、二男が株の4分の1を取得することになります。
そうなれば、経営権を巡って、長男と次男で争いが起きるかもしれません。
こういった事態を解消するために、遺留分の権利は、「全部お金で解決する」という風に法律が変わりました。
つまり、遺留分の権利を行使しても、直接遺産に対する権利は発生せず、多く遺産を受け取った人にお金を請求できる権利に変化したということになります。
このように制度が変わったことで、遺留分の問題は、比較的解決が楽になりました。
以前は、遺留分の権利を主張して、裁判等をし、その結果遺産の一部が共有物になった場合、その共有関係を解消するために、別の裁判をする必要があります。
何度も裁判をすることで、解決まで何年もかかるケースがありましたが、相続法の改正によって、短期間で遺留分の問題を解決することができるようになりました。
他にも、遺留分の制度は大きく変わった点があるため、遺留分について知りたい方は、弁護士にご相談ください。