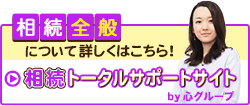今までは,遺言書は全て手書きで書かなければならないとされていました。
しかし,相続法が改正され,手書きをしなくていい部分が認められました。
具体的には,財産の特定に必要な事項については,手書きでなくても有効な遺言書として認められます。
たとえば,名古屋の土地を特定の人に相続させたい場合は,登記事項証明書(登記簿)の写しを遺言書に添付すればよいことになります。
また,特定の人に預貯金を相続させたい場合は,通帳のコピーを遺言書に添付すれば,遺産の特定としては十分です。
ただし,財産に関する書類のコピーを添付すれば,それでいいというわけではありません。
財産に関する書類のコピーには,必ず署名と押印が必要です。
コピーが数枚ある場合は,そのすべてに署名と押印が必要で,両面コピーの場合は両面に署名と押印が必要なので注意が必要です。
財産に関する書類について,上記では登記事項証明書(登記簿)や通帳のコピーを例にあげましたが,既存の資料をコピーする必要はありません。
たとえば,パソコンで財産の目録を作って,プリントアウトしたものを遺言書に添付することもできます。
ただし,あくまで書面である必要があるので,パソコンの中にデータが入っているだけでは,有効な財産目録とは認められません。
また,ICレコーダーやスマホで録音した音声データも書面ではないため,そのデータが入ったCDやUSBを遺言書と一緒に封筒に入れていても,遺産目録とは認められないため,注意が必要です。
遺言書と直接関係がないことですが,私が所属する事務所のホームページの写真が新しくなりましたので,よろしければこちらからご覧ください。