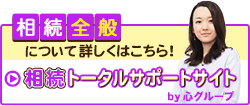人が亡くなると,相続が発生し,遺産を分けることになります。
それでは,人はいつ亡くなったことになるのでしょうか。
たとえば,臓器移植法では,「死体」から臓器を取り出すことが認められていますが,この「死体」の中には「脳死した者の身体」が含まれます。
このような生と死の境界線の議論は,医療や倫理と密接にかかわる分野であり,どの時点を人の死と考えるかは流動的です。
その他,法律の世界では,「亡くなったかどうかわからないけど,亡くなったことにしよう」という制度があります。
まず,認定死亡という制度があります。
これは,水難,火災,その他の事情で死亡したことが確実視される場合に,死体の確認ができなくても,その人が亡くなったことにする制度です。
次に失踪宣告という制度があります。
この制度は,長期間行方不明になった人を,法律上亡くなったことにする制度です。
たとえば,名古屋に住民票があるのに,住民票の住所にその人がいなくて,行方不明の状態が7年間続いた場合は,その人が法律上亡くなったと考えることになります。
また,船の沈没や,冬山登山で遭難等,危険な状態で行方不明になった場合は,1年間でその人が法律上亡くなったと考えることになります。
もっとも,ただ行方不明なだけで亡くなったことになるわけではありません。
利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする必要があります。
失踪宣告は人が亡くなったかどうかを確認せず,人が亡くなったことにする制度であるため,慎重な運用がなされています。
そのため,失踪宣告の制度を利用するのであれば,しっかりとした証拠を裁判所に提出する必要があります。
どのような証拠が必要なのかは弁護士に相談することをおすすめします。